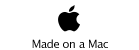豹の巣にて…
オペラハウスの老人達が不満を募らせいます。
(「化物め」という言葉がくりかえされています。)
そこへ少佐が帰投。兵士が出迎えるわけですが、ここでとってもユーゲントなネコ耳准尉とむっつりな大尉が登場。
トバルカインは吸血鬼だったらしいのですがどうやら格下だったらしく、准尉は自分たちのことを「ヴェアヴォルフ」をなのっています。
ヴェアヴォルフとはウェアウルフのドイツ語読み。つまり人狼をさす言葉なのですが、大戦中のナチスドイツにはヴェアヴォルフというゲリラ部隊が存在したようで、ここでもどうやら部隊名か何かのような意味合いで使われているようです。
そして少し遅れて老人達登場。車いすに乗っていたり杖ついていたり、大戦中のナチスの残党なので当たり前ですがみんなよぼよぼしてます。
(少佐は総統特秘第666号に基づいて活動をしているらしいのですが、この数字、「オーメン」のダミアン連想してしまいますよね。)
少佐の挑発に乗って、大佐は杖で少佐をしたたかに殴りつけるのですが、
彼らは、吸血鬼(=化物)にしてもらえないことに不満を感じていること、そして老人達以外の兵士はみな少佐の側についているということがはっきりと示されます。
1000人(一個大隊)の吸血鬼率いる少佐の目的は…
戦争の歓喜を無限に味わうために
次の戦争のために
次の次の戦争のために
だそうな。さすが、アーカードにして「狂った少佐」と言わしめるだけのことはあります。バチカンで司教が証言していた少佐のセリフがここでもまんま繰り返されているわけで、少佐の戦争狂ぶりがうかがえます。
ところで、人狼について補足。
ブラム・ストーカー版では、人狼は直接は登場しないのですが、第1章で、ドラキュラ城へと向かうジョナサンの耳に飛び込んでくる地元住民のひそひそ話の中に「人狼」「吸血鬼」がでてくるように、ルーマニアの民間伝承ではこの両者は同じようなものとしてひとくくりに扱われたり、近縁のものとしてとらえられているようです。
野生の狼の群れは何度か登場するのですが、ドラキュラ伯爵の命令をきくらしく、伯爵も狼のことを「夜の子どもたち」なんてよんでます。また、ウィトビー上陸の際には伯爵自身犬に変身しており(第7章)、吸血鬼と狼や犬が近しい関係にある様子が描かれています。
参考文献に紹介されている、ブラム・ストーカーの『ドラキュラ』関連調査資料群のなかにもルーマニアの民間伝承として吸血鬼nosferatuと人狼Prikolisch(人が凶暴な狼ないしは犬に変身する化物)の名がみえます。(文献P499)
ノートの中でブラム・ストーカーはドイツではこの迷信が廃れていると述べているのですが、どっこい半世紀後にはドイツにおいて復活を遂げ、さらに半世紀後には少佐の元に集うことになるというわけです。