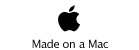いやはや7月です。
ところで先日来某ブログにて、話題にあがっていた竹取物語の「うかんるり」のくだりについて…
(本日の日記は、中学時代を思い出して先方にカキコしたところ、ちょっと色々込み入ってきたので、整理するための、管理人の個人的メモ書きですので、あしからず。この辺のいきさつに興味をもった方は、「うかんるり くま」あたりでググればたどり着けると思いますので、そちらへどーぞ。)
参考文献(主なもののみ。この他に現代語訳本をいくつか漁ってます)
1 『日本古典文学大系 9 竹取物語』阪倉篤義 他校注 岩波書店(1977)
2 『鑑賞 日本古典文学 第6巻 竹取物語 宇津保物語』 三谷栄一編 角川書店(1977)
3 『現代語訳日本の古典4 竹取物語 伊勢物語』田辺聖子訳 学研(1980)
4 『大庭みな子の竹取物語 伊勢物語 わたしの古典』大庭みな子訳著 集英社(1986)
5 『竹取物語・伊勢物語』集英社文庫 田辺聖子 集英社(1987)
6 『竹取物語・伊勢物語・落窪物語』日本古典文庫新装版 川端康成訳 河出書房新社(1988)
7 『21世紀によむ日本の古典3 竹取物語・伊勢物語』倉本由布著 ポプラ社 (2001)
問題の文章は
この女、「かくのたまふは誰ぞ」と問うに、「我が名はうかんるり」と言ひて、ふと山の中にいりぬ。
解釈としては
A 「かくのたまふは誰ぞ」と問うているのは「この女」
B 「かくのたまふは誰ぞ」と問うているのは話し手である皇子
阪倉は、文献1の補注において、「普通にとれば『この女』は『問ふ』の主語となる。が、あるいは『問ふに』といった気持ちで文がつづき『この女』は『山の中に入りぬ』の主語とみるべきか。(以下略)」として解釈Bを提示しています。
しかしこれはあくまで個人的見解であり根拠はいささか薄弱であると、阪倉自身考えていたことは、文章から容易に推察されます。
三谷はこの阪倉の見解を恐らく意識して、文献2において「『この女に』と本文を改める節もあるが、どうしても主格とみるところ。他人の氏名を問う場合、自分がまずなのるのが習慣であったから」として解釈Aの立場をとります。
大庭も解釈A。(参考文献4)
それ以外の参考文献も含め、一般に手にすることが出来る現代語訳など、出版物においては圧倒的に解釈Bが多数を
占めるのが現状です。
ところがお手軽検索でいくつかのサイトをのぞいてみると、ネット上では解釈Aもかなり普及しています。
孫引き、ひ孫引きで増殖して、結果このような現象が起きたとも考えられますが、出版物ではあくまで少数派の解釈A。70年代あたりのこの解釈が、意外とネットでは活きがいいというのは、ちょっとおもしろかったです。
ちなみに私個人としては、口承文学がベースにあるとはいえ、「本」という形をとっている以上本文を尊重したい。なので解釈A(女がたずねて、名乗って、山に入る)を支持。
この場合、女が皇子に一方的にたずねて、答えて、山に入ったとするか、皇子の返答を省略しているとするかで意見が分かれるところ。
この点に関しては私は三谷とはちょっと意見を異にします。
女にしてみれば、既に相手が男性であることは明白。見ず知らずの男性に女性の側から名乗りを上げるというのは
いささか不自然ではないかと(…あくまで素人の思い込みですが)
というわけで、皇子の返答は省略されているんだろうなぁと想像するしだい。
(センテンスの省略は決して珍しくはないですからね。)
まぁ、皇子の嘘八百ねつ造苦労話ですからね。あんまり深くつっこむコトもないのでしょうが…